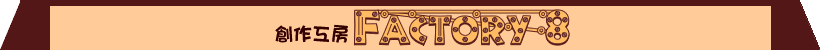
 あのころ…1990年代の音楽とその背景Sound Factoryは現在、1975年生まれの雑談とそのころの楽曲たちで進んでいますが、そもそもこの時代はどんな時代だったのか?そのころの時代背景と現在との共通点など考察していきます。 そのころの社会背景とよく流れていた曲。そしてどう行動し、音楽と向き合ったか?現在につながる原点があると思います。現在のスタイルの原点がそのころにあって、そのころの原点がもっと前にある。 第一部(1990〜1998)…「1975年生まれが体感した、音楽と社会の交差点」 ■ 第1章:始まりの鼓動 ― 青春の入口と音楽の出会い(1990〜1992)…ZOOの「Choo Choo TRAIN」がテレビから流れ、「踊れるJ-POP」という新ジャンルが生まれた。Being系(B'z、ZARD、T-BOLAN)を筆頭に、音楽が“自分の感情の代弁者”となっていた。 ■ 第2章:夜行列車と自由 ― 解放と広がりの時代(1993〜1995)…自分の足で旅をし始める時代。関西から夜行で白馬や妙高、山陰や九州へ向かったあの頃――夜行列車は、まさに「自由」の象徴だった。音楽では、Beingの隆盛の終焉とともに、小室哲哉プロデュースが台頭。TRF、globe、安室奈美恵のような“踊れる時代”がやってくる。一方、FM802がこの流れに抗う姿勢を見せ、リスナーの分断が起こる。 ■ 第3章:混迷と再生 ― 社会の中での音楽の意味(1995〜1998)…阪神・淡路大震災という現実が襲い、音楽が「心の支え」として再認識された時代。希望と現実のはざまで、多くの若者が自分の居場所を探していた。MISIA、BONNIE PINK、Sakura、R&B系の内省的な音楽が都市生活者の心をつかみ、JR西日本が手がけたクラブやイベントスペースが新しい文化を育てるきっかけとなる。就職氷河期でつまずきながらも、自分で“人生を選ばざるを得ない”フェーズへ突入していく。 第1章:ZOOとChoo Choo TRAIN ― ダンスが音楽と若者文化を変えた瞬間…“パフォーマンス型グループ”という新しいスタイルが生まれた時代 第2章:夜行列車と音楽の旅 ― カセットとMDに詰め込んだ思い出…「夜行列車×音楽」=ひとつの旅のスタイル 第二部(1998〜2002)〜静かに起きた革命、音楽の重心が変わった時代 第4章:ループが語り始めた ― HIPHOPと新しいJ-POPの胎動(1998〜1999):1998年夏、嶋野百恵のデビューはまだ静かだったが、そのトラックにはZOOやEASTEND以上に“HIPHOPの文法”が自然に織り込まれていた。 年末に宇多田ヒカルが「Automatic」でシーンを一変させる。ループビートと英語的発声、従来のJ-POPにないプロダクション。 しかも彼女はテレビに出ない。それでもチャート1位、ロングセールス。テレビという“通過儀礼”を拒否した最初の成功者だった。 第5章:対抗と融合 ― 倉木麻衣と“関西産”へのまなざし(2000〜2001):倉木麻衣の登場は、Beingの再定義でもあり、関西発の音楽に対する“東京からの警戒”の現れでもあった。 デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」は、サイバーサウンドによるボストン仕込みのトラックと、J-POP的な聴きやすさの融合。 強烈なHIPHOPビートは抑えつつ、ループを基調にした「聴きやすいHIPHOP」が大衆へと届いた。 この動きは、EXILE、KICK THE CAN CREW、KREVA、Soul'd Outといった00年代HIPHOP〜R&Bのベースを築く布石となった。 1975年生まれにとって高校時代から20代までの間の音楽の状況は激変した状況を体感したが、1982年生まれにとってはそれがあたりまえになっている。そんな1982年生まれにとってその後の音楽はどう見えたのだろうか? 第三部(2002〜2010年)三つの分岐と、1982年生まれの音楽的現実 第6章:R&BとHIPHOPが日常になる:私たちの音楽が“社会の音楽”になる瞬間 第7章:「アイドル」がメインになるという悪夢:資本と疑似恋愛の侵食 第8章:中田ヤスタカという中庸の旗印 〜音楽性とアイコンの狭間で〜 第四部:解放 ― 多様化する音楽と世代の接続点 第9章(2011年以降)スマホの中の音楽 ― YouTube、サブスク、SNS 1975年生まれにとってあたりまえにあった音楽が実は以前の世代にとって革命的な事が起きたことは、新しい流れが1982年生まれにとってあたりまえの音楽として捉えられていることから確か。ではその当時の音楽の源流はどの時代なのだろうか? 第五部:音楽の新しい流れの源流 ― 1970年代の革新と1980年代の転換期 第12章:1963年生まれの青春期(1978〜83年頃)に起きた音楽の大変化 第13章:山口百恵の引退(1980年)=テレビ的歌謡曲の終焉 |