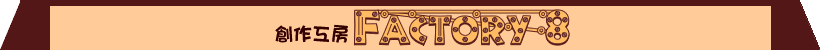
 第四部:解放 ― 多様化する音楽と世代の接続点第9章:「スマホの中の音楽 ― YouTube、サブスク、SNS」2008年にiPhoneが登場し、2011年ごろにはスマートフォンが一般化しはじめた。これにより、音楽を聴くという行為は「部屋」や「ステレオコンポ」「CDプレイヤー」のような“定位置”を持ったものから、「移動しながら」「SNSを眺めながら」「イヤホン越しに他人と切り離された状態で」聴くものへと変わった。 1982年生まれが10代後半〜20代を過ごした時代、音楽は「自分を表すもの」だった。友人関係の中で「何を聴いているか」はステータスであり、CDや雑誌で得た情報が会話の糸口になっていた。しかし2010年代以降、「音楽が主語になる会話」は急速に消えていく。それは、音楽が“文化”ではなく“気分”や“背景”になる時代への移行だった。 YouTubeがもたらしたのは、MVを中心とした「視聴体験としての音楽」である。曲単体ではなく、映像とセットで体験する。これは明らかに、テレビ的な受け取り方から、ネット的な「自分で選び、再生する」能動性を持った行為への変化だ。 SpotifyやApple Musicに代表されるサブスクリプションサービスの浸透も大きい。アルバムを通して聴く、という前提は崩れ、「気分」や「タグ」に応じたプレイリスト消費が当たり前になった。「今売れている曲」より「今の自分の気分に合う曲」こそが、優先されるようになった。 さらにTikTokの台頭によって、音楽は“断片的に消費される素材”となった。1コーラスどころか15秒でどこまでフックを作れるか。つまり、音楽はメッセージではなく“現象”として共有されるものになったのだ。 |