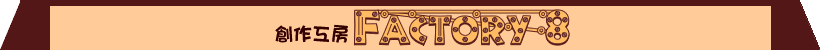
 第10章:ボーカロイドとセルフプロデュースの時代この時代のもう一つの大きな転換点は、「作る人」の民主化である。かつて音楽を作るにはレコード会社の支援や、スタジオでのレコーディング、機材を揃えた環境が必要だった。しかし、パソコン1台とソフトウェアさえあれば、誰でも楽曲を“商品”として世に出せる時代が到来した。 象徴的なのがボーカロイド文化の拡張だ。2007年に初音ミクが登場し、2008〜2012年頃には“DTM出身”のアマチュアたちが、ニコニコ動画に楽曲を投稿して名を上げていった。彼らは「顔を出さず」「キャラを立てず」、ただ“曲そのもの”と“映像”の力で共感を得ていた。 1982年生まれにとって、音楽とは“演奏するもの”であり、誰かのパフォーマンスを聴くものであった。しかし、彼らにとって音楽とは、“打ち込むもの”であり、“視覚と音響が一体化したアウトプット”である。 さらに重要なのは、こうした作家たちが「自分で自分を売り出す」必要があったという点だ。レコード会社ではなく、YouTubeやSNSで再生数を伸ばし、自己ブランディングを確立していくスタイルは、ある意味、芸能産業そのものの価値体系を変えていった。 そこに「声優」や「Vtuber」、「ライバー」の台頭が重なる。音楽は「自分の物語を届ける手段」として再定義され、「うまさ」や「プロっぽさ」は二の次になっていく。重要なのは、「自分という存在に共鳴するファン層を作れるか」という点に移行していく。 |