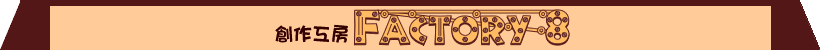第二部(1998〜2002)〜静かに起きた革命、音楽の重心が変わった時代
プロローグ
1998年の夏、嶋野百恵が静かにデビューを果たす。ZOOやEAST ENDを超えるような、洗練されたHIPHOPのループが散りばめられた彼女のサウンドは、商業的には決して大成功とは言えなかったが、音楽的には明らかに時代の転換を告げていた。そして、その波は年末にデビューする宇多田ヒカルへと確かに受け継がれていく。
宇多田ヒカルの『Automatic』、倉木麻衣の『Love, Day After Tomorrow』――この2曲が1998〜2001年の日本の音楽シーンに与えた衝撃は、テレビを通さずFMやCDショップ、そして口コミとネットを通じて静かに、だが確実に広がっていった。それは、従来のテレビ中心型プロモーションが支配していたJ-POPの構造に亀裂を入れるものであり、「テレビで見たことないのに、誰もが口ずさめる曲」という新しい現象を生んだ。
実はこの背景には、両者の家庭的な事情も大きく関わっていた。宇多田ヒカルは母・藤圭子の存在、倉木麻衣は父・山前五十洋との関係から、従来の“芸能”システムを避けざるを得なかった。そしてそれが、かえって彼女たちを「音楽そのもの」で勝負する姿へと導いたのである。
宇多田照實(ヒカルの父)や長戸大幸(Being/GIZA)のように、大衆が好むコード進行や構成にHIPHOPやR&Bの要素をブレンドする手法は、まさに嶋野百恵が切り開いたスタイルの進化形だった。彼女たちはループ、英語詞、重心の低いリズムといった新しい“聴き心地”を、日本語ポップスのフィールドに落とし込むことに成功する。
だが、宇多田がすでにシーンを席巻する中で、倉木麻衣が「二番煎じ」と呼ばれるリスクは大きかった。GIZAはこの懸念に対し、サウンド面での差別化を図るため、ボストンのCyber Soundに編曲を依頼し、海外制作による匿名性と本格感を獲得した。特に『Never Gonna Give You Up』は、HIPHOP、R&B、UKソウル、ポップスが融合した、GIZA流“洋楽的J-POP”の完成形と言えるだろう。
この流れの中で、テレビに依存しない新しいアーティスト像が定着し、EXILE、KREVA、Soul’d Outといった「次のHIPHOP世代」にも静かに火を灯していく。それは、“テレビで売る”時代から“聴かれて浸透する”時代への明確な転換点だった。
第4章:静かなる始まり、HIPHOPの内在化
1998年に登場した嶋野百恵は、東京や大阪のクラブシーンを知る者にとっては新鮮でありながら、どこか「遅れて来た本物」として迎えられた存在だった。彼女の音楽は、派手なサビやバブル的な盛り上げを排除し、ループやビート、そして黒人音楽の文法に忠実なフロウを重視したもので、当時のJ-POPにはほとんどなかった「内省的な高揚感」を備えていた。
このスタイルは、BPMの選び方やコード進行、声の重ね方において、のちの宇多田ヒカル、さらには倉木麻衣の楽曲に確かな影響を与えている。特に、嶋野百恵が見せた「HIPHOPの感性をJ-POPに溶かす」試みは、音楽そのものに新しい重心をもたらした。嶋野の影響を受けたアーティストは、音を“浴びるもの”から“感じ取るもの”へと再定義していく。
宇多田ヒカルのデビューは衝撃的だったが、それは決して“突然現れた天才少女”という物語だけではない。彼女の音楽には、母・藤圭子の影、そして父・宇多田照實の冷静なマーケティング感覚が色濃く投影されている。
特筆すべきは、テレビを避けたプロモーション戦略だ。ヒカルは音楽番組にほとんど出演せず、代わりにFM局や雑誌、街中のCDショップなど、“耳”と“手”で広がるルートを選んだ。彼女の音楽は顔よりも先に「音」で届き、ビジュアルの印象が固定されないままヒットを飛ばした。それゆえ、リスナーの多くは楽曲を“自分のもの”として受け止めやすかった。テレビに出ない。それでもチャート1位、ロングセールス。テレビという“通過儀礼”を拒否した最初の成功者だった。
また、照實が構築したサウンドは、徹底して洋楽文法に根差していた。ループ構造、ボーカルのダブ処理、シンコペーション――それらが日本語と違和感なく混ざることで、J-POPという枠組みを無効化し、「現代の都市生活者に合う音楽」として機能したのである。
TOP← 第1章← 第2章← 第3章← 第4章 →第5章 →第6章 →第7章 →第8章
|