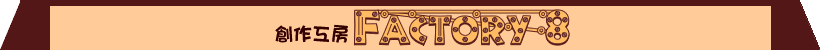
 第2章:夜行列車と音楽の旅 ― カセットとMDに詰め込んだ思い出1990年代、関西から夜行列車で旅に出るという行為は、ある種の“通過儀礼”だった。 夜、友人たちと集合し、リュックひとつで列車に乗り込む。目的地は白馬山麓や妙高高原、あるいは山陰や九州。そんな旅の道中で欠かせなかったのが、音楽だった。WalkmanやMDプレイヤーから流れる曲たちは、夜行列車のきしむ音と交差しながら、特別な記憶として刻まれていく。 急行「きたぐに」、快速「ムーンライト九州」「ムーンライト山陽」、そして夏の海水浴シーズンに臨時で走ることのあった「サロンカーなにわ」など、鉄道旅行の風情がまだ生きていた時代。その中で青春のサウンドトラックとして流れていたのは、globe、TRF、安室奈美恵、小室哲哉サウンド。テンポのいいダンスビートが、夜の車窓と交差するとき、そこには不思議な高揚感があった。 「夜行列車×音楽」=ひとつの旅のスタイル。 音楽を聴くという行為が、単なる娯楽ではなく、「誰とどこへ行ったか」「何を感じたか」と深く結びついていた。たとえば白馬へのスキー旅では、TRFの「寒い夜だから…」が、まさにテーマソングになったような感覚すらあった。夜の列車で聴いた音楽が、ゲレンデの空気にそのままリンクしていく。 この頃、若者は「自分だけのプレイリスト」をカセットやMDで作り、旅に持っていった。FM802で録音したランキング番組からお気に入りの曲を選び抜き、A面・B面の流れまで考えて編集する作業は、もはや芸術的でもあった。 列車の中では、窓の外に流れる町の灯りをぼんやり見ながら音楽に浸る時間。友達と喋るでもなく、ただ並んで音楽を共有する沈黙の時間があった。現在のBluetoothイヤホンやスマホでは味わえない、“空気ごと音楽を共有する”文化だった。 夜行列車が減り、音楽がスマホでストリーミングされるようになった今、その空気感を体験することは難しいかもしれない。だが、「移動しながら音楽を聴く」「音楽と風景が一体になる」という感覚は、今でも旅の本質のひとつだ。 現代の若者がもし“夜行旅”を体験するなら、ぜひ自分でプレイリストを作ってみてほしい。そして、ただ「聴くだけ」ではなく、「音楽と風景が交わる瞬間」を探してみてほしい。Z世代もミレニアルも関係なく、「音楽と旅が心を動かす」原点が、そこにはある。 |