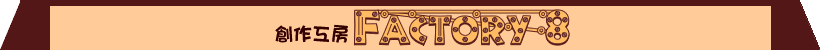
 第3章:音楽と社会の分岐点 ― 混迷と再生のはざまで1995年前後、日本は音楽も社会も大きな分岐点を迎えていた。 90年代前半、ZOOやEAST END×YURIの登場が「ダンス×ヒップホップ×J-POP」という新しい感覚を生み、音楽に“身体性”が加わった。そして、長戸大幸プロデュースのBeing系(B'z、T-BOLAN、WANDS、ZARDなど)がチャートを席巻していた時代――だが、時代の熱狂はやがてピークアウトし、小室哲哉を中心とした新たなムーブメントが席巻していく。 小室ファミリー(globe、TRF、安室奈美恵、華原朋美など)の爆発的ブームは、90年代中盤を代表するサウンドとなった。特に安室奈美恵の登場は「ギャル文化」と結びつき、音楽だけでなくファッション・生き方そのものに大きな影響を与える。 しかし、その流れに一石を投じたのが、関西発のラジオステーションFM802の“沈黙”だった。 当時の802は、Being系や小室ファミリーの楽曲をあえて「オンエアしない」方針を取った。大阪の音楽シーンで“反主流”を貫く姿勢が、かえってリスナーの共感を失い、一時的な低迷期へと入っていく。だがその裏で、BONNIE PINK、MISIA、Sakura、UA、スガシカオなど、よりソウルフルでR&B色の強いアーティストが次々と登場し、若者の「本質的な音楽志向」に火をつけていく。 またこの時期、JR西日本が大阪駅高架下にプロデュースしたクラブ(後のQOO梅田につながる)が登場するなど、関西ならではの都市型音楽文化も芽吹き始めた。音楽と都市とが融合する新たな感覚だった。 しかし、こうした新しい流れに水を差すように、1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生。関西圏に住む人々、特に若者たちにとって「当たり前」が崩れたあの瞬間、音楽は再び「娯楽」ではなく「心の支え」になった。 避難所で流れるラジオから、静かに響いていたのは希望をつなぐようなメッセージソング。震災をきっかけに、SION「Sorry Baby」や、中島みゆきの「空と君のあいだに」など、言葉に力を持つ楽曲が再評価された。 音楽が、現実から逃げるものではなく、現実と向き合うための伴走者であるという認識が、強く刻まれた時代でもある。 この時期に大学を卒業した若者たちは、“就職氷河期”という言葉に苦しみながらも、自分たちのスタイルを模索していた。社会は不安定で、景気は悪化。だがその中で、「自分の声を持つ」アーティストと、それを求める若者たちが確実に育っていた。 音楽と社会が強くリンクしていたこの時代は、単に「ヒット曲」を追いかけるだけでは語れない。それぞれの街、それぞれの暮らしの中に“必要な音楽”があった。そしてその音楽たちは、あの震災を越えたとき、より深い意味を持って人々の中に残っていった。 |