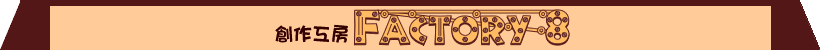
 第11章:個人と共鳴する音楽 ― 米津玄師からAdoへこうした変化を象徴的に体現したのが、米津玄師だった。彼はボーカロイドPとして始まり、そこから自ら歌い、ジャケットもMVも自ら手がけた。「全部自分でやる」という姿勢は、商業音楽の在り方に対するひとつのアンチテーゼだった。 彼の音楽には、センチメントと孤独、物語性と映像性が共存していた。かつてテレビに登場してスターとなることが“成功”だった時代に比べ、米津はテレビに出ずしてドームを埋めるアーティストになった。それはまさに、新しい“信頼”のあり方を示していた。 続いて登場したAdo、ずっと真夜中でいいのに。、YOASOBIといった存在たちも、顔を見せない、名前も芸名、存在は半分フィクション、というスタンスをとる。だがそれでも、多くの人に共鳴を呼んだ。それはつまり、「誰かの“現実”である必要がなくなった音楽」が生まれたということだ。 これは、「AKB的な疑似恋愛の消費構造」へのカウンターでもある。恋愛の対象ではなく、“共鳴の対象”であること。推すのではなく、自分の痛みや希望を代弁してくれる存在として支持するという関係性。 また、ここに来て、音楽のジャンルすらも無意味になっていった。ヒップホップ、ロック、アイドル、クラブ…というカテゴライズはもはや時代遅れであり、楽曲単位で「刺さる」かどうかだけが重要になった。 |