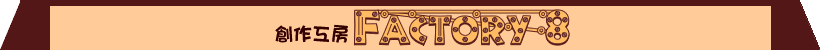
 第5章:「似ている」と言わせないための選択一方、宇多田の成功があまりに鮮烈だったため、後発となった倉木麻衣は“二番煎じ”と見られるリスクと常に隣り合わせだった。だからこそ、プロデューサーである長戸大幸は徹底して「差別化」を図る必要があった。 まず取ったのが、音の質の変化だ。GIZAはボストンのCyber Soundに編曲・トラック制作を依頼する。これは国内スタジオでは得られない“洋楽的洗練”を獲得するためであり、同時に「大阪発ではあるが、ローカルではない」という戦略的メッセージでもあった。デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」は、Cyber Soundによるボストン仕込みのトラックと、J-POP的な聴きやすさの融合。そして『Never Gonna Give You Up』は、まさにその象徴である。R&Bのフィーリング、HIPHOP由来の低域のグルーヴ、そしてメロディアスなポップ性が見事に交差し、宇多田とは異なるベクトルで「洋楽的J-POP」を確立した。 また、倉木自身がテレビに登場しなかったのも、父親との関係性や家庭環境が大きく影響していたと言われている。テレビ露出を避けつつ、音だけで語る――それは宇多田と同じ道を辿りながら、異なる経路での到達を意味していた。 この時代、音楽はテレビからラジオ・CD・口コミ・ネットへと、その流通経路を変えていった。90年代を席巻したテレビ・タイアップ型のヒットモデルはここで限界を迎える。CDの売上が伸び悩む中でも、宇多田や倉木のように「テレビに出ない」スタイルが成立。音楽ファンは自ら選び、掘るようになる。 音楽を“聴いて好きになる”のではなく、“見せられて好きになる”時代が終わりを告げ、リスナーが自分の耳と感覚で選び取る時代が到来していた。EXILE、KREVA、m-flo、Soul’d Outなど、00年代の新しい音楽潮流もまた、この“テレビの外側”で力を蓄えたアーティストたちだった。 音楽は「テレビに出るための道具」ではなく、「直接心に届く言語」へと役割を変えたのである。 宇多田も倉木も、実は東京に寄らないという大阪のスタイルとは無縁ではない。特に倉木麻衣のGIZAは、大阪・北堀江のカルチャーを背景にしながら、あえて東京に寄せないプロモーションを展開した。それは、Being時代の教訓でもあった。90年代半ば、東京の音楽関係者やメディアは、大阪発のBeing(B'z、ZARD、T-BOLANなど)を“テレビに出ないのに売れる存在”として半ば敵視していた。これは、単なる音楽性の違いではなく、「東京=中心」という意識への挑戦に見えたからだ。 その対抗構造は、宇多田・倉木の時代にも引き継がれていた。だが大阪の音楽家たちは、対抗心ではなく“文化の地続き”の中で外来音楽を取り込み、自らの形にしていくことが得意であり、1300年続く国際都市の柔軟さでもあった。東京のイノベーターたちが大阪の動きに敏感なのも、無意識に感じているその“異質性”ゆえなのかもしれない。 |