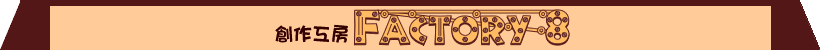
 第五部:音楽の新しい流れの源流〜1970年代の革新と1980年代の転換期
|
| 生まれ年 | 文化的位置づけ | 音楽的志向 | メディア支配 |
| 〜1960年 | 体制に回収されがち | 若い時はロック→中年で演歌・歌謡曲へ回帰 | ラジオ/テレビ/新聞 |
| 1955年前後 | 反体制の最初の音楽世代 | ソウル、R&B、日本語ロック | ライブ重視・雑誌/FM |
| 1963年 | 選択可能な分岐点 | フォーク、洋楽、ニューミュージック、ブラックミュージック | FM/MTV/テレビ混在 |
| 1975年 | テレビに引き戻されつつも多様性拡大 | J-POP/クラブミュージック/HIPHOP | テレビ→ネット過渡期 |
第13章:山口百恵の引退(1980年)=テレビ的歌謡曲の終焉
● 山口百恵は、テレビを軸にした「全員参加型の音楽時代の象徴」。
● 引退をもって、以下の構造が揺らぎ始める:
・ 分業による歌謡曲(職業作詞家・作曲家・編曲家+歌手)・巨大メディアによる「国民的ヒット」強制
歌謡曲の「終わり」とJ-POPの「はじまり」
| 時期 | 中心文化 | 内容 | 世代との関係 |
| 〜1980年頃 | 歌謡曲(全世代共有) | 山口百恵、ピンクレディー、演歌も含む | 1963年生まれ=青春真っただ中 |
| 1980年代前半 | ニューミュージック/シティポップ | 荒井由実(ユーミン)、サザン、オフコース、竹内まりや | 1975年生まれ=小中時代に吸収 |
| 1985年〜 | 「アイドルの再定義」by 秋元康 | おニャン子、バラドル、歌よりトーク重視 | 歌謡曲のバラエティ化=共感より消費 |
| 1990年代〜 | J-POP本格化、ブラック/クラブ系流入 | 小室哲哉、ミスチル、ドリカム、嶋野百恵など | 1975年生まれが青春=選択肢の多様化へ |
第14章:1950年前後生まれ(1948〜1955年)の音楽体験
この世代は、「J-POP前史」の実験者・開拓者でもあり、1975年生まれの感性に強く影響を与えた“兄貴分”のような存在。
1. グループ・サウンズとビートルズの衝撃(1960年代後半)
● ザ・タイガースなどのGSブームとビートルズ来日(1966)が同時進行。
● 初めて「洋楽的サウンド」を日本語でやろうとした世代。
2. ソウル・R&B・ブルースの日本的再解釈(1970年代前半〜中盤)
● 上田正樹(1974)、桑名正博(1978)、柳ジョージらによって、“日本語でグルーヴする音楽”が本格化。
● 洋楽への憧れを超えて、「日本語に宿るソウル」への模索と表現。
3. ライブ・フェスカルチャーの出現(1970年代後半〜1980年代初頭)
● 野音や万博公園などでの野外ライブの文化が形成される。
● スタジオ録音より「ライブこそ本物」という価値観。
● → これは後のサマソニ/フジロック文化の前身。
終章:「新しい音楽の流れ」とは何だったのか
● 洋楽的感性 × 日本語の身体性 = “J-POP前夜”の音楽
● この流れを受けた1963年生まれ世代は:
・YMOで電子音楽への目覚め・中島みゆきで歌詞に心を映し・ 桑名正博や柳ジョージで「日本語のブルース」を知る
・ 深夜放送で音楽の“探究心”を育てた
■ 1963年生まれが体験した音楽の源流は、「洋楽的自由」と「日本語表現の可能性」の交差点にあった。
この原体験は、90年代以降のJ-POPの成熟、クラブ文化、あるいはYouTube世代の音楽体験にも根を下ろしている。
時代の分岐:ざっくりとした傾向
| タイプ | 内容 | 代表アーティスト | 傾向 |
| 歌謡曲継承派 | 親しみやすさ、テレビ中心、哀愁 | 松田聖子、中森明菜、安全地帯、チェッカーズ | 昭和の情緒を大切にしがち |
| ニューミュージック 〜J-POP進化派 |
個人的表現、作詞作曲志向 | ユーミン、サザン、オフコース →ミスチル、ドリカム |
情感+ポップの洗練 |
| クラブ/R&B/ブラック派 | ダンス、グルーヴ感、個のリズム | m-flo、bird、嶋野百恵、ZEEBRA | カルチャーとしての音楽 |
| アイドル消費派 | 可愛さ、物語性、推し文化 | おニャン子→モー娘→AKB | 商品としての音楽 |